
またケンカして…!
そう思わずため息をついたこと
ありませんか?
毎日のように繰り広げられる
兄弟ゲンカ
ちょっとしたおもちゃの取り合いや
どっちが先にお風呂に入るかといった
些細なことから、
時には本気の怒鳴り合いまで。

親としてはイライラしたり
不安になったり
「なんでこんなに仲が悪いの?」と
心配になることもあるでしょう。
でも実は、その“兄弟ゲンカ”こそが
子どもたちの心を育てる
「筋トレ」だとしたら……?
今日は、兄弟ゲンカを
「成長のチャンス」として捉える視点と
親としてどう関わればよいのかについて
お話ししていきます。
兄弟ゲンカが起こる理由
まず、なぜ兄弟ゲンカが絶えないのか。
それは、兄弟という関係が
「避けられない関係性」だからです。
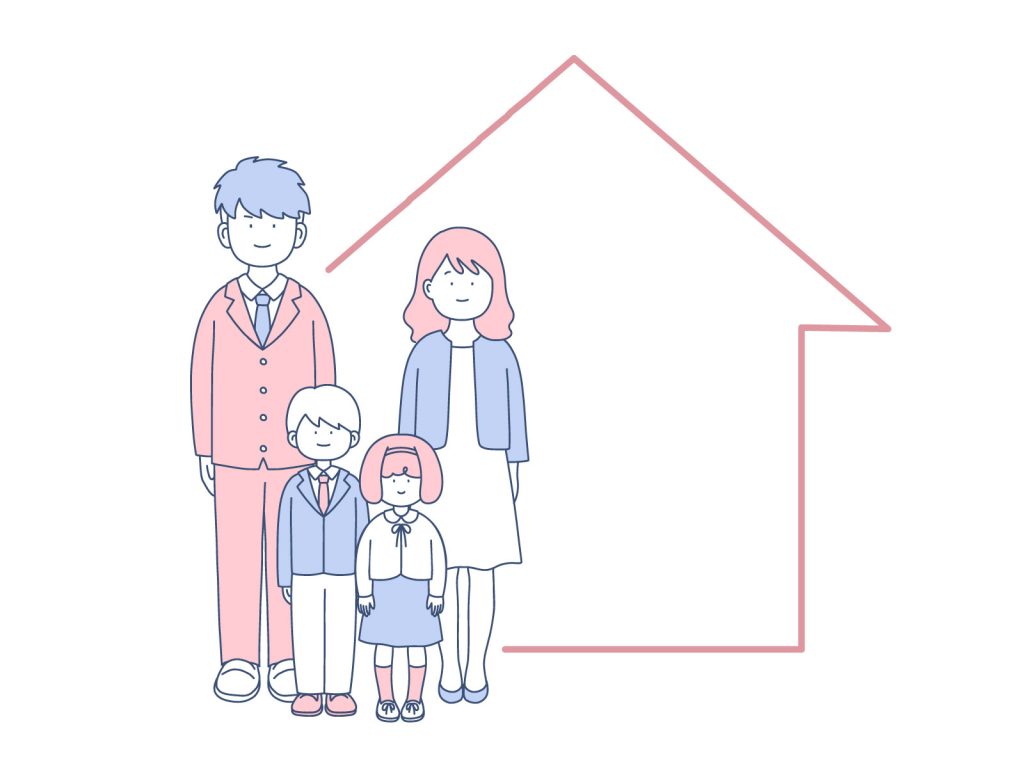
保育園や学校の友達なら
ケンカして気まずくなったら
距離を置くこともできます。
でも兄弟は同じ家に住み
同じ親を持ち
逃れようのないつながりの中で
生活しています。
しかも、年齢や発達段階の違い
親からの愛情の感じ方の違い
「お兄ちゃんだから」
「妹なのに甘えてばかり」などの
役割期待や不公平感も重なり
感情がぶつかりやすいのです。
つまり、兄弟ゲンカは
「関係性の中で自分を主張し
相手と調整していく練習」の場
でもあるのです。
兄弟ゲンカは心の「筋トレ」
子どもはケンカを通じて
次のようなことを学んでいきます。
・自分の気持ちを言葉にする力
・相手の反応を受け止める経験
・譲ることの難しさと大切さ
・負けた時のくやしさ、勝った時の後味
・和解するための手段やタイミング
これらはすべて
将来社会で必要になる
「対人関係スキル」の土台です。
まさに、心の筋トレ✨💪
毎日兄弟げんかをすることで
少しずつ
「感情のコントロール」や
「交渉する力」が育っていきます。
もちろん、親にとっては
ストレスの種にもなりますが

この子たちは今、大事なトレーニング中なんだ!
と思えば
少し見方が変わってくるかもしれませんね。
では、親はどこまで介入する?
ここが一番悩ましいところですよね。
放っておいても
エスカレートしそうだし
かといって、すぐに止めたら
子どもたちの成長の機会を奪ってしまうかも…

ポイントは
「完全に放任しない」
「すぐに裁定者にならない」ことの2点✨
1. 見守る
まずは、一度深呼吸。

子どもたちのやり取りに
耳を傾けてみてください。
感情的になっていても
自分の主張を言葉にしようとしていたり
なんとか相手を
説得しようとしていたりするかもしれません。
暴力や強い言葉で
傷つけあっていない限りは
少し様子を見ることで
自分たちで解決する力が育ちます。
2. 「通訳」として入る
小さな子どもの場合
言葉で感情を表現するのが難しくて
手が出てしまうこともあります。
そんなときは、
どちらが悪いかを判断するのではなく
「通訳者」として関わってみましょう。
たとえばこんなふうに

〇〇ちゃんは、おもちゃをまだ使いたかったんだね

△△くんは、それを急に取られてびっくりしたのかもしれないね
子どもたちの気持ちを代弁することで
「自分の気持ちが理解された」
「相手にも気持ちがある」と感じられ
心が落ち着きやすくなります。
3. 安全だけは守る
もちろん
叩く・蹴る・ものを投げるといった
行動があれば
それはしっかり止める必要があります。
ただし
「怒ってはいけない」
「けんかしてはいけない」
と感情を否定するのではなく
「叩いてしまうほど怒ったんだね」
「でも、叩くのは相手も痛いから
他の伝え方をしようね」

と、気持ちに寄り添いつつ
行動を制限する姿勢が大切です。
親の役割は「仲裁」ではなく「対話のサポート」
兄弟げんかを見ていると
つい
「どっちが悪いの?」
「なんでこんなことでけんかするの!」
と裁定者になってしまいがちです。
でも、子どもにとって大事なのは
「自分の気持ちを理解してもらえること」

そして
「相手にも気持ちがある」と気づくことです。
親の役割は、正解を示すことではなく
子ども同士の対話をサポートすること。
たとえば、こんな問いかけが有効です。

〇〇ちゃんはどう思ってるの?

△△君はどうして、それがだったのかな?

じゃあ、次はどうしたらよさそう?
このような“対話”を積み重ねていくことで
兄弟げんかの質が
少しずつ変わってきます。
最初は怒鳴り合いだったものが
やがて
「言葉で交渉できるケンカ」に
育っていくのです。
まとめ&おわりに
兄弟ゲンカは、親にとっては
ストレスでしかないように感じることもあります。
でもその背景には
子どもたちが「自分らしさ」と
「他者との関わり方」を
模索している姿があります。

ケンカを通して
自分の気持ちを知り
相手とぶつかり
調整していく力が育っていきます。
まさに、心の筋トレ💪
親とは
「すぐに止める人」でも
「裁く人」でもなく
「対話を支える人」であることを
意識してみてください。
「見守る力」
「寄り添う言葉」
そして何よりも
「このケンカもきっと意味がある」と
信じるまなざしが
子どもたちの成長を
大きく後押ししてくれるはずです。
今日もがんばるあなた自身にも
どうぞ優しいまなざしを
向けてあげてくださいね✨




