子どもが何かをがんばったとき
つい言いたくなる言葉がありますよね。
「すごいね!」
「えらいね!」
「よくできたね!」
そんな言葉に
子どもが嬉しそうな顔を見せてくれると
つい何度もほめたくなる。
これは親として、
とても自然な反応です。
けれど、アドラー心理学では
「ほめる」と「勇気づけ」は
まったく違う意味を持つと考えます。
似ているようで、実は
子どもの心に届く“メッセージ”が
まったく違うのです。

「ほめる」と「勇気づけ」はどう違うの?
「ほめる」という行為は
基本的に“評価”が前提です。
「〇〇ができたから、すごいね」
「成績がよかったから、えらいね」
というように、
行動や結果を見て
上から判断を下すような
関わり方になりがちです。
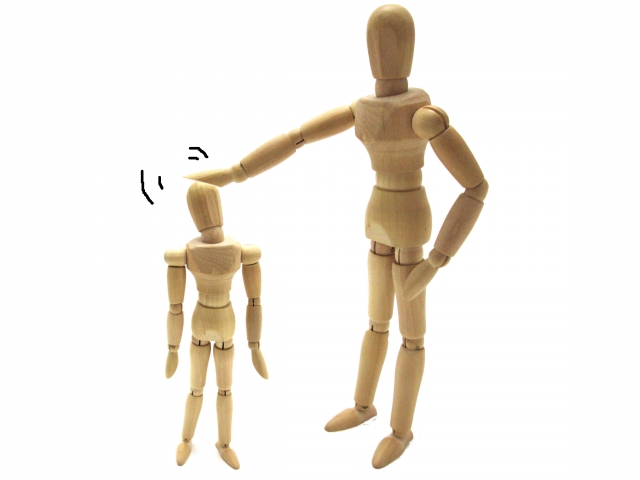
一方、「勇気づけ」は
子どもの存在や努力、気持ちに寄り添う
コミュニケーションです。
評価ではなく
“信頼”と“共感”がベースにあります。

たとえば、こんな違いがあります。
| シーン | ほめる | 勇気づけ |
| 子どもが 手伝いをしたとき | 「えらいね 助かったよ!」 | 「ありがとう 助かったよ」 |
| テストで いい点をとったとき | 「すごいじゃん 100点なんて!」 | 「努力してたもんね。 自分でも嬉しいでしょ?」 |
| 弟におもちゃを 貸したとき | 「やさしいお兄ちゃんね!」 | 「自分から貸せたんだね いい気分だった?」 |
勇気づけには
「あなた自身を信じてるよ」
「自分の力でやってごらん」
という
温かなメッセージが含まれています。
「ほめられた子」と「勇気づけられた子」のちがい
では、子どもたちは
それぞれ
どう育っていくのでしょうか?
ほめられて育った子
ほめられて育った子は、
「よく思われたい」
「認められたい」
という気持ちが強くなりがちです。
その結果、
評価されることに敏感になり
うまくいかないときに
自信を失いやすくなったり
「どうしたらほめられるか」
に意識が向きすぎて、
自分の本音が
分からなくなることもあります。
勇気づけられて育った子
一方、勇気づけられて育った子は、
「自分には価値がある」
「そのままでいいんだ」という
土台が育っていきます。
誰かに認められるためではなく
自分の納得と
充実のために
行動するようになるのです。
自発性
挑戦する力
困難に向き合う粘り強さ——
そうした生きる力は
「あなたの存在を信じている」という
親のまなざしの中で育まれていきます。
勇気づけの子育て、親が心がけたいこと

じゃあ、もうほめちゃダメなの?
そんなふうに思われた方も
いるかもしれません。
もちろん、褒めること自体が
悪いわけではありません。
ただ、
「ほめなきゃ」
「いいところを探さなきゃ」と無理をすると
親のほうが疲れてしまったり
子どもへの“期待”が
重たくなってしまうこともあります。
勇気づけの子育てで大事なのは
評価ではなく
「見守ること」
「信じること」
「寄り添うこと」
それは
「子どもを操作しない」
ということでもあります。
子どもが失敗したときや
がんばってもうまくいかなかったときこそ
「よくやったね」
と言いたくなる気持ちを
少しおさえて
「悔しかったね」
「それでもあきらめなかったね」
と、感情や過程に寄り添ってみる。
それが、何よりの勇気づけになるのです。
勇気づけってどうやるの?具体例あれこれ
では実際に、
日常の中でどう勇気づけを
取り入れたらいいのでしょうか?
ここでは、すぐに使える
フレーズや工夫を
いくつかご紹介します。
◯ 子どもの気持ちを映す
「緊張してたんだね」
「それ、イヤだったよね」
→ 感情に寄り添ってもらえると
子どもは
“わかってもらえた”と
安心感を得ます。
◯ プロセスに目を向ける
「毎日ちょっとずつ続けてたもんね」
「工夫してたの、見てたよ」
→ 結果より
努力や工夫を認めてもらえると
次もがんばろうと思えます。
◯ 子どもの存在を喜ぶ
「あなたがいてくれて、うれしい」
「一緒にいて楽しいよ」
→ 存在まるごとを肯定されると
子どもは自然と前向きになります。
⚠️注意したいこと:無理をしない、正解を求めない
勇気づけは
「言い換えテクニック」
ではありません。
大事なのは、
“親のまなざし”と
“子どもとの関係性” です。

完璧な勇気づけなんて
ありません。
落ち込む日
イライラする日
余裕のない日もあって
当然です。
そんなときは
自分自身にも「よくやってるよね」と
声をかけてあげてください。
親が自分に優しくできると
自然と
子どもにも優しくなれます。

勇気づけは、子どもだけでなく
親の心も育ててくれる関わり方なんです。
まとめ:ほめるより、信じて寄り添う
「ほめる」は評価がベース
「勇気づける」は信頼と共感がベース
勇気づけられた子どもは
自分の価値を自分で感じ
前向きに
行動できるようになります。
親は、子どもの感情や努力
存在そのものに
目を向けることがポイント。
完璧な対応は不要ですよ✨
親子の関係をあたためることが
一番の目的
子育ては、
答えのない旅のようなもの。
だからこそ
「できた/できない」ではなく
「どうあたたかくつながっていくか」
その視点から
今日の親子のやりとりを
そっと見直してみませんか?




