夏休みが終わりに近づくころ
親として少しホッとする気持ちと同時に
子どもの様子に
不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
「学校に行きたくない…」
「やる気が出ない…」
そんな言葉を子どもから聞かされると
つい焦って
「またサボるつもり?」
「ちゃんと行きなさい!」
と叱りたくなってしまう。
でも、親がどれだけ正論をぶつけても
子どもの気持ちは
前を向いてくれないことがあります。
では、そんなとき子どもは
どんな言葉を待っているのでしょうか?
夏休み明けの「不適応感」は自然な反応
臨床心理学の分野では
長期休暇明けの子どもが
「学校に行きたくない」と感じるのは
珍しいことではないとされています。
環境の変化や
生活リズムの乱れが
心理的ストレスとなり
意欲の低下や
不安感として表れるのです。

これは“怠け”や“わがまま”ではなく
心理的適応に
必要な過程のひとつ。
大人でも
長期休暇後に仕事に行くのが
憂うつに感じられるように
子どもにとっても
「再適応」には時間がかかります。
子どもが欲しいのは「正解」よりも「安心」
子どもが
「学校に行きたくない」と口にしたとき
多くの親は
「どうして?」
「理由を言ってみなさい」
と問い詰めがちです。

しかし実際のところ
子ども自身も
理由を言葉にできないことが
少なくありません。
なんとなく不安
なんとなく疲れた
気持ちが追いつかない…
そうした感覚は
大人でも説明が難しいものですよね。
そんなときに一番欲しいのは
正しい解決策ではなく
「安心感」

「そっか、しんどいんだね」
「長い休み明けって
大人でもエンジンかかりにくいんだよ」
そう共感してもらえるだけで
子どもは
「自分の気持ちをわかってくれた」と感じ
少しずつ心が軽くなっていきます。
こうした共感的な言葉は
子どもに
「自分の気持ちを否定されなかった」
という安心をもたらします。
これこそが勇気づけの基盤です。
親が意識したい“勇気づけ”の姿勢
STEPでは
「勇気づけ」が
子育ての土台になると考えられています。
勇気づけとは
単に「がんばれ!」と
励ますことではありません。
子どもが「自分は大切な存在だ」と
感じられるように関わること。

これが勇気づけの本質です。
例えば
「頑張ったから偉いね」
ではなく
「あなたの気持ちを大事に思ってるよ」
「大丈夫、ゆっくりでいいよ」
「○○のこと、信じてるからね」
叱咤激励ではなく
子どもの存在そのものを
認めるような言葉。
これが子どもの背中を
そっと支える力になります。
親が持ちやすい「焦り」とどう向き合うか
とはいえ、子どもが
「行きたくない」
と言うたびに共感するのは
親にとっても
簡単ではありません。
心のどこかで
「また始まったらどうしよう」
「このまま引きこもったら…」
と不安や焦りが顔を出します。

そんなときに大切なのは
「自分の焦りをそのまま子どもにぶつけない」
ということ。
子どもを
守りたい気持ちが強ければ強いほど
つい
「甘えないで」
「しっかりしなさい」
と厳しい言葉になってしまいがちです。
でもその言葉は、子どもに
「自分の気持ちは理解されない」
と感じさせ、
孤独感を強めてしまい
さらに気持ちを閉ざしてしまいます。
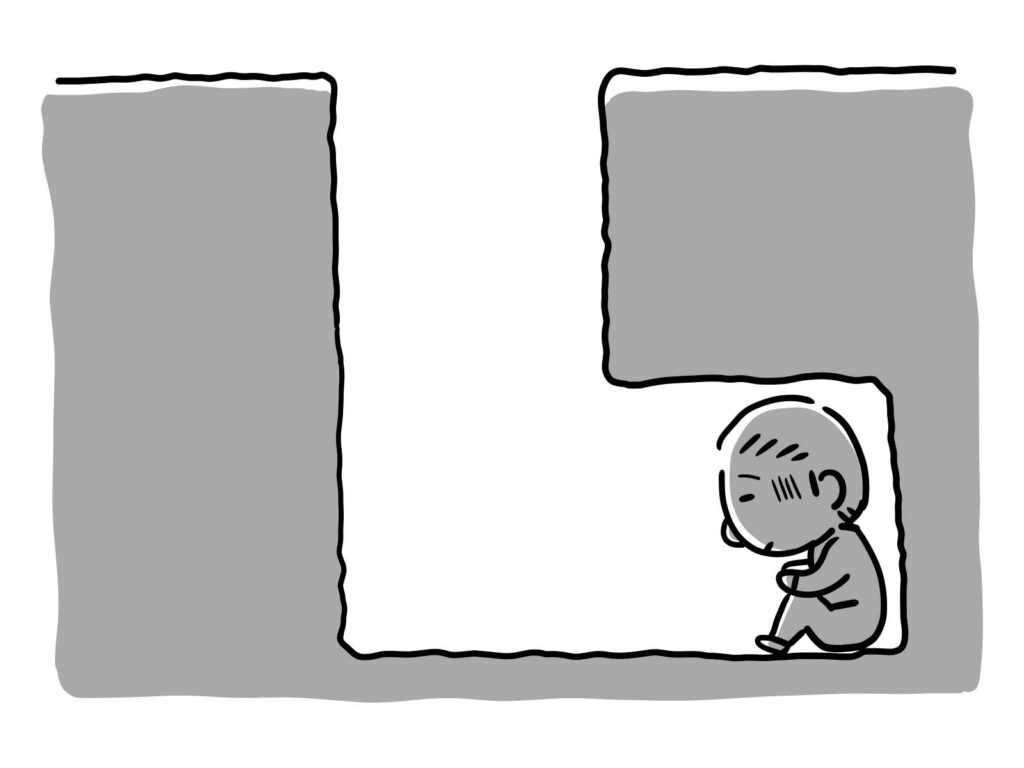
親自身が
「大丈夫!
時間はかかってもウチの子は回復していく」
と信じられるかどうかが
子どもの心を支える大きな力になります。
心理学ではこれを
「自己充足的予言(Self-fulfilling prophecy)」
と呼びます。
親が信じることで
子どもは無意識に
「信頼されている自分」に
ふさわしく行動しようとするのです。
子どもはどう変化していくのか
勇気づけの言葉を受け取った子どもは
すぐに元気いっぱい!
劇的に変わるわけではありません。
でも少しずつ表情が柔らかくなり
自分の気持ちを
話そうとし始めます。
「今日はまだ休みたい」
から
「明日は行けるかも」に
「勉強いやだ」
から
「この教科だけはやってみようかな」に
小さな一歩を踏み出す姿が
見えてくるでしょう。
子どもが
“自分は大切な存在なんだ”
と感じられると
不安やしんどさの中にあっても
「挑戦してみよう」という力が
湧いてくるのです。
こうして子どもは少しずつ
「行動する勇気」を取り戻していきます。
大切なのは、
その小さな一歩を親が見逃さず
価値づけていくことです。
夏休み明けは“親子でリズムを作るチャンス”
夏休みが終わるころは
生活リズムも乱れがち。
朝の時間や
就寝時間を一緒に整えることも
子どもにとっては
大きなサポートになります。
「一緒に早寝早起きしようか」
「朝ごはんは一緒に食べよう」
こうした日常の中での小さな関わりも
子どもに安心感を与えます。
「自分は一人じゃない」
「伴走してくれる人がいる」
と感じられることが
学校へ向かう力につながっていきます。

心理学的に言えば
これは
「安心のアタッチメント(安全基地)」を
強化する働きがあります。
親が共に日常を整えてくれることは
子どもにとって
「自分は支えられている」という
確かな実感につながるのです。
まとめ&おわりに
子どもが
「学校に行きたくない」と言い出した時
親はつい焦ってしまいます。
知っていて欲しいのは
それは「怠け」ではなく
心理的適応の過程における
自然な反応であるということ。
そして子どもが
本当に欲しているのは
「解決策」ではなく
「安心感」ということです。
叱りつけるのではなく
存在そのものを認める言葉が
子どもにとって
最大の勇気づけになります。

勇気づけとは
「あなたは大切な存在だ」と伝えること
親の焦りを子どもにぶつけず
安心と信頼を届けること
小さな一歩を共に喜び
生活リズムを整えることが
心理的支援につながっていきます。
勇気づけの関わりは
子どもに「挑戦してみよう」という力を
育みます。
夏休み明けの不安定な時期は
親子の信頼関係を深める
絶好のチャンスです。
勇気づけの言葉を
一つひとつ積み重ねながら
子どもの心に
「大切にされている」という安心を
届けていきましょう。




