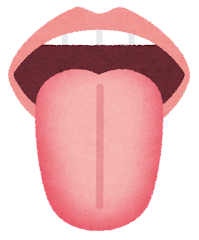雨あがりのスカッと晴れた日
心もカラダも感じられませんか?
気持ちはもちろんスッキリするのを
感じられると思いますが、
身体が軽く感じることも多いと思います。
逆に雨の日、
外出先で急な土砂降りに遭い
びしょ濡れになってしまった経験は
ありませんか?
冷たい水が肌に張り付き
不快感で動きも鈍くなり
早く乾いた服に着替えたくて仕方がない…
実はこの感覚
東洋医学でいう
「痰湿(たんしつ)」という体質の状態に
とてもよく似ているのです。
痰湿(たんしつ)とは
身体の余分な水分を
溜め込みやすい体質。
「むくみやすい」とおっしゃる人の中に
このタイプの人が
多くいらっしゃるのも事実。

今回の記事は
「痰湿」という体質について
今回は、
「痰湿ってなに?」
「どうしてそうなるの?」
「改善するにはどうしたらいいの?」
という疑問にお答えしながら
体がスッキリ軽くなるための
ヒントをお届けします。
「痰湿」とはどんな体質?
「痰湿(たんしつ)」とは、
体内の水分代謝がうまくいかずに
不要な水分(湿)や
粘り気のある老廃物(痰)が
たまってしまった状態です。
体の中に
ベタベタとした湿気がこもり
巡りが悪くなることで
さまざまな不調を引き起こします。
体感として良く例えられるのは
「水に濡れたべたべたの服を
着たまま生活している」状態
・重だるく倦怠感がある
・風が吹くと、とたんに寒さを感じやすくなる
・腰から下がやたらと冷える
・肩が凝り、頭痛を伴うことも など
これらの症状はすべて
体に余分な「水」がたまっているサイン。
まるで、
濡れた服が肌にまとわりついて
動きづらくなるように、
体内の湿気が邪魔をして
スムーズな代謝や血流の流れを妨げているのです。

服はカラッと乾いていて
キレイなモノが着たいと思いませんか(*´罒`*)
ここで言う「痰(たん)」とは
西洋医学で言われる
喉にへばりつく「痰」とは「似て非なるもの」で
目には見えない痰と
目に見える痰があります。
この体質では健康が維持できず
体の様々な部位に
不調が起きやすくなります。
「痰湿」の主な特徴
むくみや肥満
痰湿の代表的な症状で
余分な水分が排出されずにたまるため
手足や顔にむくみが起きやすくなります。
悪化すると
「たくさん食べていないのに太る」という
水太りになる可能性があります。
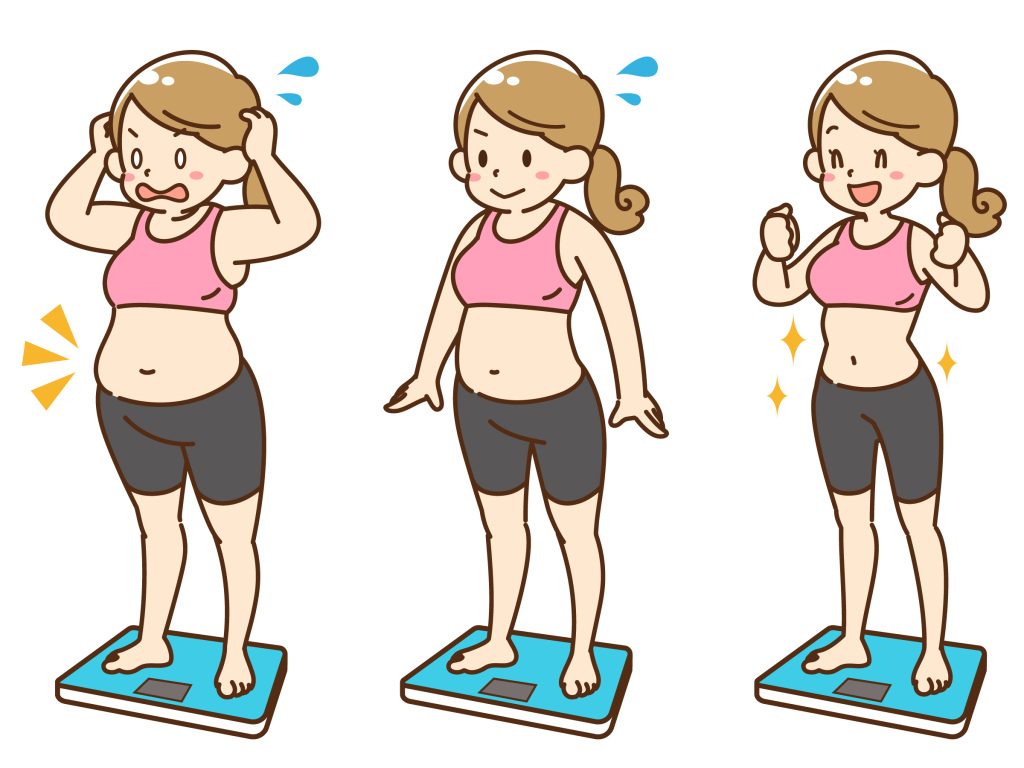
余分な老廃物は
セルライトになることがあり
体重増加や肥満に繋がることがあります。
倦怠感
痰湿が原因の倦怠感は
体が重くだるさを感じることや
むくみ
胃部の不快感などの症状を伴います。
体内の巡りが悪くなり
エネルギーが低下しがちです。
消化不良
痰湿が胃腸に溜まると働きが低下しやすく
食欲不振や消化不良
便秘や下痢などの
消化器系の問題が起こりやすくなります。
のどの渇き
しっかり水分を摂っているのに
のどの渇きを感じる場合は
痰湿によって体内で
水分がうまく巡っていないことがあります。
さらなる水分摂取で
症状が悪化することもあるので
注意が必要です。
めまいや吐き気
痰湿が原因のめまいは
水分代謝が悪くなり
頭部に痰湿がたまることが
主な原因と考えられています。
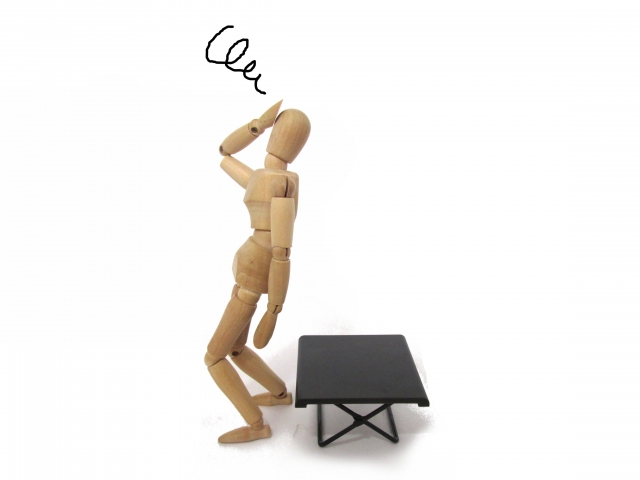
吐き気や頭重などの症状も伴うことが多いです。
オイリー肌
体内の痰湿が皮膚から溢れている状態です。
白く化膿があまりみられないニキビ・吹き出物
顔色も白く
熱感がないのが特徴です。
「痰湿」体質になる原因は?
痰湿の原因はさまざまですが
主に以下のような
生活習慣や体質が関係しています。
1. 食生活の乱れ
甘いものや脂っこいもの
冷たい飲み物を好む人は要注意です。
これらは「脾(ひ)」と呼ばれる
消化吸収をつかさどる臓腑の働きを弱め
水分代謝を悪化させます。
特に現代の食生活では
スイーツやコンビニフード
冷たいドリンクが当たり前になっており
知らず知らずのうちに
「痰湿体質」を育てている可能性があります。
2. 運動不足
運動をしないと
体の巡りが滞り
余分な水分を汗や尿として
排出しづらくなります。
また、代謝が落ちることで
体が冷え
湿気がさらに体にたまりやすくなります。
3. 湿気の多い環境
梅雨の時期や
ジメジメとした気候の地域では
外からの「湿」が
体内に入り込みやすくなります。
特に日本のような
高温多湿の気候では
「痰湿体質」になりやすい傾向があります。
4. ストレス・睡眠不足
ストレスや慢性的な疲れ
睡眠不足も「脾」の働きを弱め
水分代謝を妨げる原因になります。
気の巡りが滞ることで
水の巡りも滞りやすくなります。
痰湿を改善するための対処法
では、この厄介な「痰湿」を取り除き
体をスッキリ軽くするためには
どうすればよいのでしょうか?
ポイントは、
「脾」を健やかに保ち
余分な水分をしっかり排出できる体に
整えることです。
1. 食事の見直し
まずは食生活から✨
利水作用のある食材:はと麦、冬瓜、小豆、とうもろこし、きゅうり
脾を元気にする食材:山芋、かぼちゃ、キャベツ、とうもろこし、玄米
温める食材:生姜、ねぎ、シナモン、紅茶
一方で
冷たい飲み物やアイスクリーム
生野菜の過剰摂取(体を冷やす)
脂っこいもの
甘いスイーツ
加工食品
アルコールの過剰摂取
体を冷やさず
「消化しやすい」
「温かい」食事を基本にすると
脾の働きが整い
自然と湿気を追い出せるようになります。
2. 適度な運動
ウォーキングやストレッチ、ヨガなど
軽い運動で十分です。
とにかく体を動かし
巡りをよくすることが大切。
汗をかくことで
余分な水分を
排出する効果も期待できます。
3. 湿気対策を意識する
梅雨や夏場は特に
「除湿」を意識しましょう。
エアコンの除湿機能を活用したり
布団をこまめに干す
湿気のこもらない服装を選ぶなど
日常生活の中でも湿を避ける工夫を。
4. 漢方薬の活用
症状が強く出ている場合は
漢方薬の力を借りるのも一つの手です。
痰湿に効果があるとされる
代表的な処方には
以下のようなものがあります。
平胃散(へいいさん):脾の機能を整え、湿気を取り除く
二陳湯(にちんとう):痰の排出を促す
五苓散(ごれいさん):体内の水分バランスを整える
体質や症状に合わせた
漢方薬を選ぶためには
専門家による相談が大切です。
自己判断せず
信頼できる漢方薬局や
中医師のアドバイスを受けてください。
5.生活習慣の見直し
規則正しい生活を心がけ、
十分な睡眠をとります。
質の高い睡眠は
体の回復を助け
痰湿の蓄積を防ぎます。
ストレスは痰湿の発生を悪化させるため
適度なリラックスも必要です。
まとめ&おわりに
「痰湿」は
体にとってまさに
“余分なお荷物”。
濡れた服を着続けるような
不快感を抱えながら生活している状態は
想像以上に
心身のバランスを崩してしまいます。
でも、生活習慣の見直しと
薬膳・漢方の力を借りれば
少しずつ体は軽やかに変わっていきます。
まずは「ちょっと疲れが取れにくいな」
「なんとなく体が重いな」という
小さなサインに耳を傾けてみましょう。
今日からできる小さな一歩が
あなたの体調を
根本から整えるきっかけになるかもしれません。
痰湿を取り除いて
さらりと軽やかに
健やかな毎日を手に入れましょう。