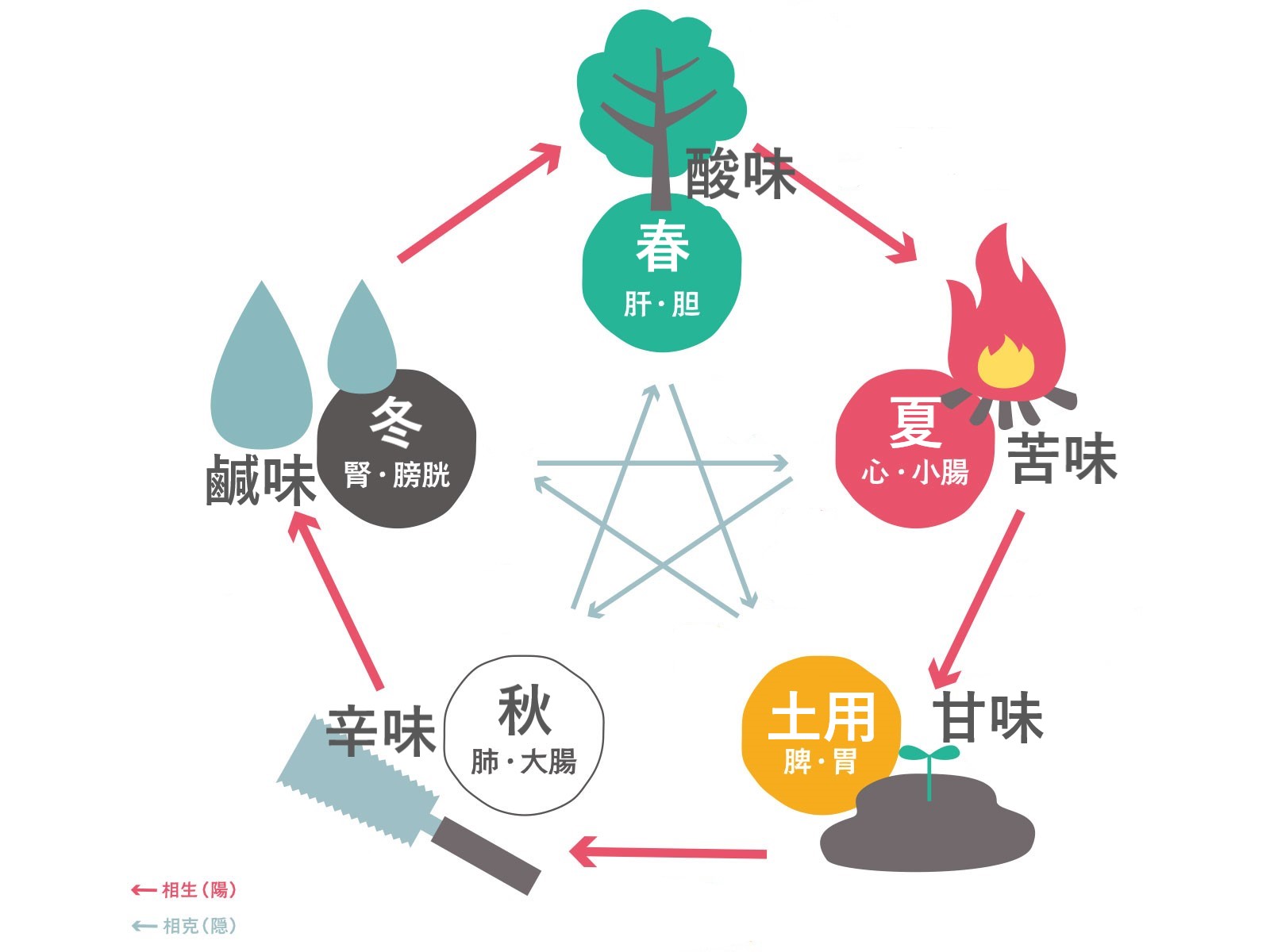「四季」でなく
「五季」(笑)
『春夏秋冬のほかに
季節があったのかしら???』
って思われるでしょう。
(私は思いました)
漢方の世界は
陰陽五行説の思想に従っているため
5つ目の季節があるのですよ(*’ω’*)
では、5つの「季節」を
一緒に学んでいきましょう!
5つの季節「五季」とは?
通常1年は
「春・夏・秋・冬」の四季に分かれていますが
漢方の世界では
陰陽五行に則して
「土用」と加えた五季に分類されています。
「土用の丑の日」として
夏だけのイメージが強いかもしれませんが
実は土用は年に4回
すべての季節の“変わり目”に
存在する特別な時期。
漢方ではこの土用を加えて
「五季(ごき)」とし
心と体のバランスを整える重要な期間として
位置づけています。
| 五季 | 二十四節気 | |
| 春 | 立春(りっしゅん)~清明(せいめい) | 2/4頃~4/5頃 |
| 春の土用 | 穀雨(こくう) | 4/20頃 |
| 夏 | 立夏(りっか)~小暑(しょうしょ) | 5/5頃~7/7頃 |
| 夏の土用 | 大暑(たいしょ) | 7/22頃 |
| 秋 | 立秋(りっしゅう)~寒露(かんろ) | 8/7頃~10/8頃 |
| 秋の土用 | 霜降(そうこう) | 10/23頃 |
| 冬 | 立冬(りっとう)~小寒(しょうかん) | 11/7頃~1/5頃 |
| 冬の土用 | 大寒(だいかん) | 1/20頃 |
「五季」に合わせた食養生
五臓の働きは、「五季」と関連しています。
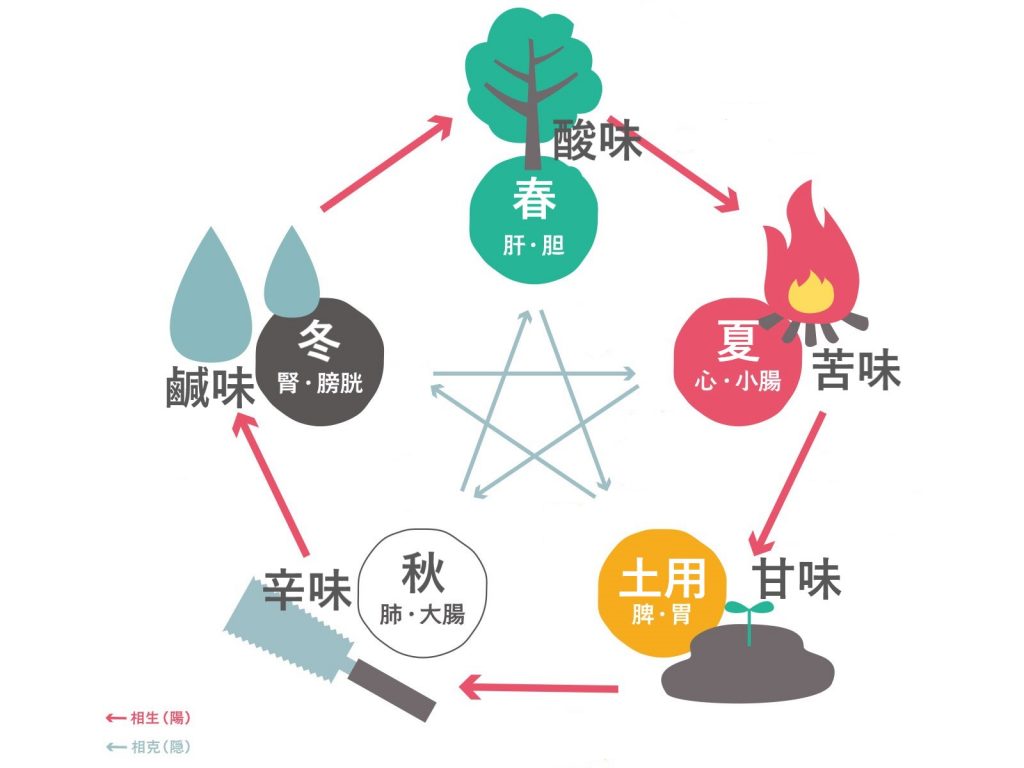
上のイラストを例えにみていきましょう。
春は「肝」を傷めやすい季節で
適度な「酸味」を摂り
「肝」を養生し、
次の季節の臓腑である
「心」を養生します。
夏は「心」を傷めやすい季節で
適度な「苦味」を摂り
「心」を養生し、
次の季節の臓腑である
「肺」を養生します。
秋は「肺」を痛めやすい季節で
適度な「甘み」を摂り
「肺」を養生し、
次の季節の臓腑である
「腎」を養生します。
冬は「腎」を痛めやすい季節で
適度な「鹹味(かんみ)」を摂り
「腎」を養生し、
次の季節の臓腑である
「心」を養生します。
季節の間に「土用」が入りますが
ちょうど季節の変わり目に当たるため
「脾」を養生していきます。
「適度」 →『相生関係』
日常の食事においても
五味をバランス良く
「適度」な量を体に摂り入れることで
『相生関係』により
各臓器がグルグル順調に働き
体調が良い状態を生み出します。

「過度」→『相剋関係』
反対に「過度」になりすぎると
「相剋関係」が発生します。

例えば、
酸味を摂りすぎると肝が弱り
さらに胃の調子が悪くなります。
そこから負の連鎖が発生していくことを
意味しています。
五季それぞれにふさわしい食養生
「適度」な食生活や過ごし方は五行を整え
「過度」になるとバランスを崩す
この考えをもとに
五季それぞれにふさわしい
食養生を見ていきましょう。
🌸春(木):「肝」をゆるめて、のびやかに
春は自然界も人の身体も
縮こまっていたものが一気に伸びていく季節。
ですが、肝が過剰になると
イライラや頭痛
目の疲れが起きやすくなります。
酸味:梅干し、酢の物、柑橘類
香り:三つ葉、しそ、せり
緑の葉物:小松菜、菜の花
酸味と香りで“気”を巡らせ
肝の働きを助けましょう。
ただし、酸味の摂りすぎは
脾に負担をかけるので“適度に”
☀️夏(火):「心」をいたわり、陽気を調える
夏は陽気が最高潮に達し
汗とともに「気」や
「津液(水分)」が失われやすい時期。
心に負担がかかると
不眠や焦燥感が現れることも。
おすすめ食材
苦味:ゴーヤ、ピーマン、セロリ
水分補給:すいか、トマト、麦茶
清熱作用:緑豆、はと麦
体を冷やしすぎず
心の熱を落ち着ける食材を取り入れて
冷たいものの摂りすぎは胃腸に要注意⚠️
⛰️土用(土):「脾胃」を整えて、変化に強い身体へ
季節の変わり目にあたる土用は
体調を崩しやすい
「見えない季節」
湿気・冷え・暑さが入り混じるこの時期こそ
消化器系のケアが最優先です。
おすすめ食材
甘味(自然な):かぼちゃ、さつまいも、山芋
湿を取る:冬瓜、とうもろこし、はと麦
胃にやさしい:おかゆ、雑炊、煮物
冷たいもの・生もの・油ものは控えめに。
“胃腸を休ませる”ことが
次の季節に向けた準備になります。
🍂秋(金):「肺」を潤し、乾燥に備える
空気が乾いてくる秋は
肺や皮膚が敏感になりやすい時期。
喉の痛み、咳、肌荒れが出やすくなります。
潤い食材:梨、白きくらげ、れんこん
発散と補潤:大根、ねぎ、生姜
ナッツ類:松の実、くるみ
体の内側から潤すことが大切。
軽く温めながら
辛味で気の巡りも促していきましょう。
❄️冬(水):「腎」を養い、温めて蓄える
冬は「腎」の季節。
エネルギーをしっかり蓄え
春に備えるときです。
冷えや疲労感
むくみが出やすくなります。
温める:黒豆、黒ごま、にんにく
根菜類:ごぼう、人参、山芋
塩味のある食材:わかめ、昆布、味噌汁
温かい煮込み料理や
スープで体の芯から温めましょう。
冷えは万病のもとです。
まとめ:季節の“橋渡し役”である「土用」を意識して暮らす
「春夏秋冬」というサイクルの中に
四つの土用(春土用・夏土用・秋土用・冬土用)が
入り込むことで、
私たちは自然の変化に
無理なく対応できるようになります。
五季を意識した暮らしは
決して特別なことではありません。
✔ 朝の空気の変化に気づく
✔ 食べたいものを「体が何を求めているか」と考えてみる
✔ 胃腸が重い日は、おかゆでリセットする
そうした小さな行動の積み重ねが
体調改善や
未病の予防につながるのです。
「五季のリズムに寄り添う」
それは、自然に逆らわず
あなたの心と体の声に
耳を傾ける優しい生き方です。
心とカラダは繋がっています✨✨
カラダの不調が
心に影響し
心の不調が
カラダに影響を与えることも。
「考えすぎてしまう」
「気持ちの切り替えが上手くなりたい」
「すぐに他人と比べてしまう」
そんな自分を変えたいとお考えなら
勇気づけ勉強会「STEP」に
参加されませんか?
アドラー心理学を軸に
子育てはもちろん
さまざまな人間関係のトラブルを
解決する知識と手法を
トレーニングによって学ぶことが出来ます!
勇気づけセミナー「STEP」しゃくしゃく
LINE公式アカウントを開設しています✨
お友達追加の特典として
「STEP」プチ講座の無料動画を
プレゼント!🎁
↓ぜひお友達登録してくださいね♪↓
https://www.muji.net/lab/food/170830.html 無印良品「五色を食べる」
https://yakuzen-komachi.jp/topics/4075 薬膳小町「五行学説(五行色体)」