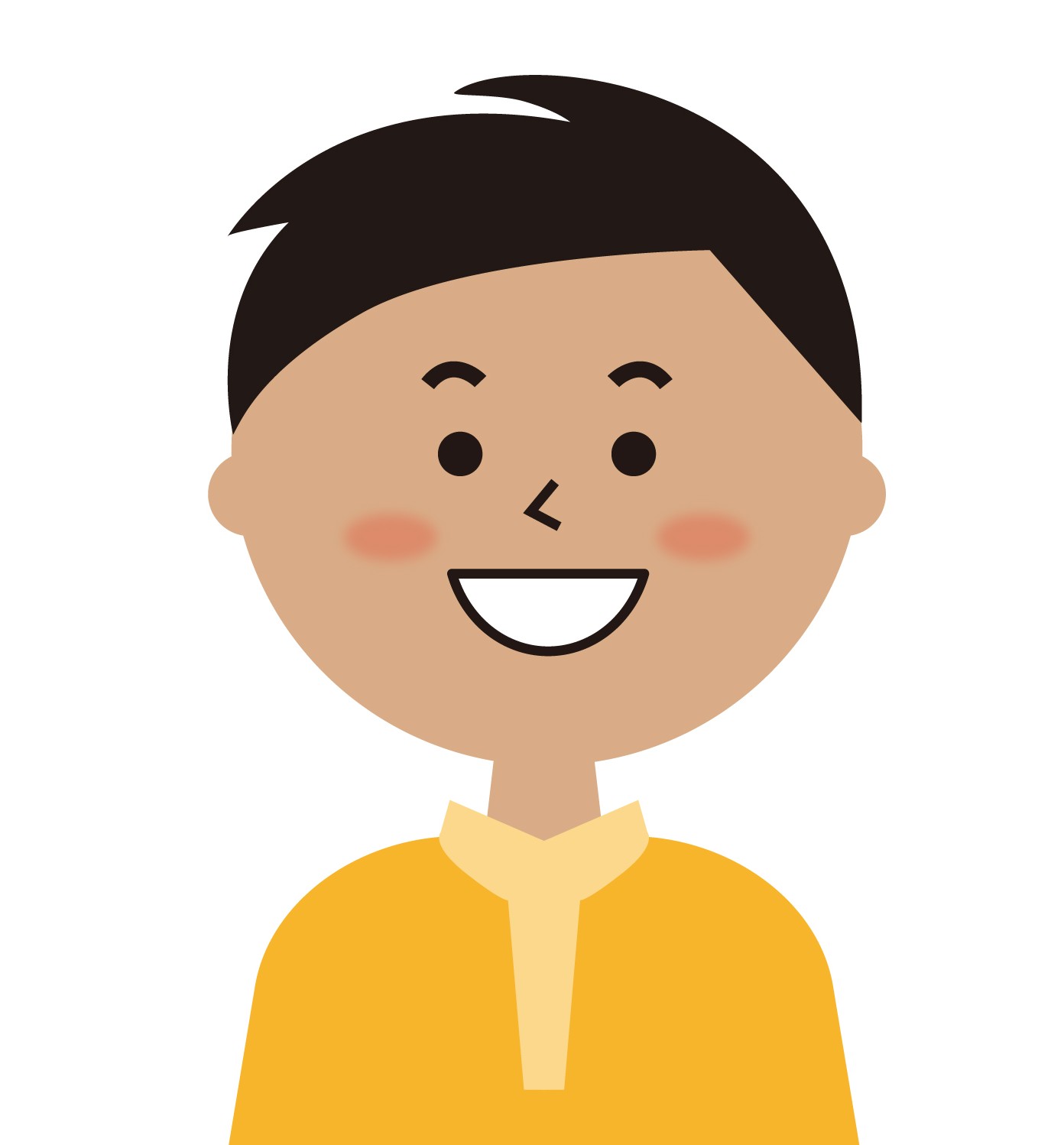
お母さん、やってみたい!
そんな子どもの声に、つい

今は時間がないから…

危ないから、あとでね
と言ってしまったこと、ありませんか?
親として、
子どもの安全や効率を考えて
「先回り」してしまうのは
ごく自然なことです。
でも、それが積み重なると
子どもの「やってみたい!」という気持ちは
どこへ向かうのでしょうか。
今回は、
子どもの自主性を育てるために
なぜ「待つ」ことが大切なのか
そしてそのために
親ができる
心の準備や対話の工夫について
一緒に考えてみたいと思います。
「やりたい!」は、自主性の芽
子どもの
「やりたい!」という言葉には
自主性の芽が宿っています。
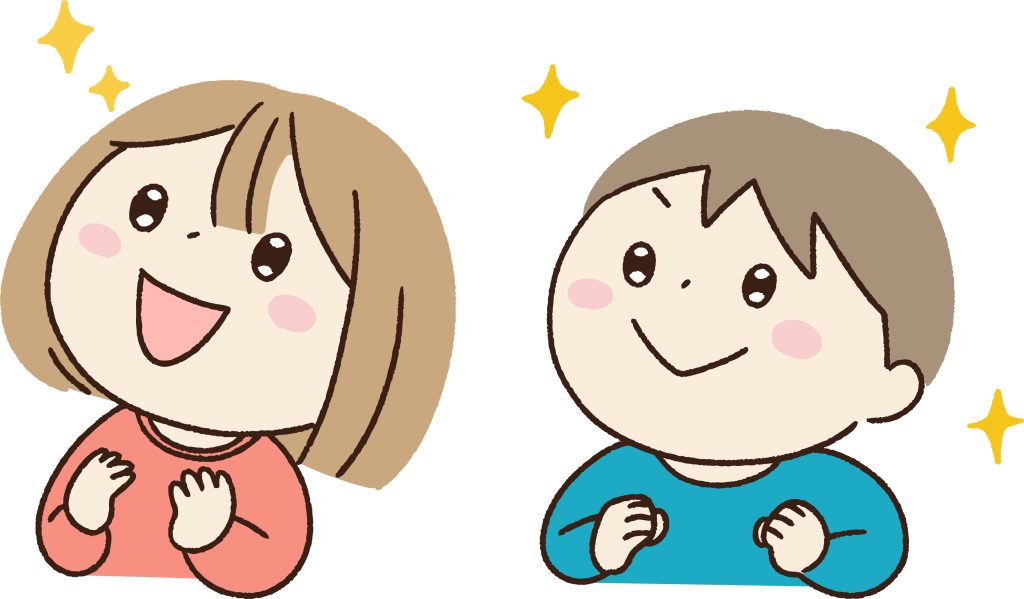
それは、
「自分で考えたい」
「できるか試したい」
「大人と同じようにやってみたい」という
成長のエネルギーです。
このエネルギーは
子どもが自分自身を信じ
学び
挑戦していくための土台になります。
だからこそ、
大人がその芽を大切に扱い
折ってしまわないようにしたいものです。

でも、親の立場になると
この「やりたい!」を
そのまま受け止めるのは
意外と難しいもの。
忙しい日常の中では
「時間がない」
「危ない」
「余計に手間がかかる」
「失敗したらどうしよう」
といった不安や焦りが
先に立ちますよね。
親に求められる「待つ力」とは?
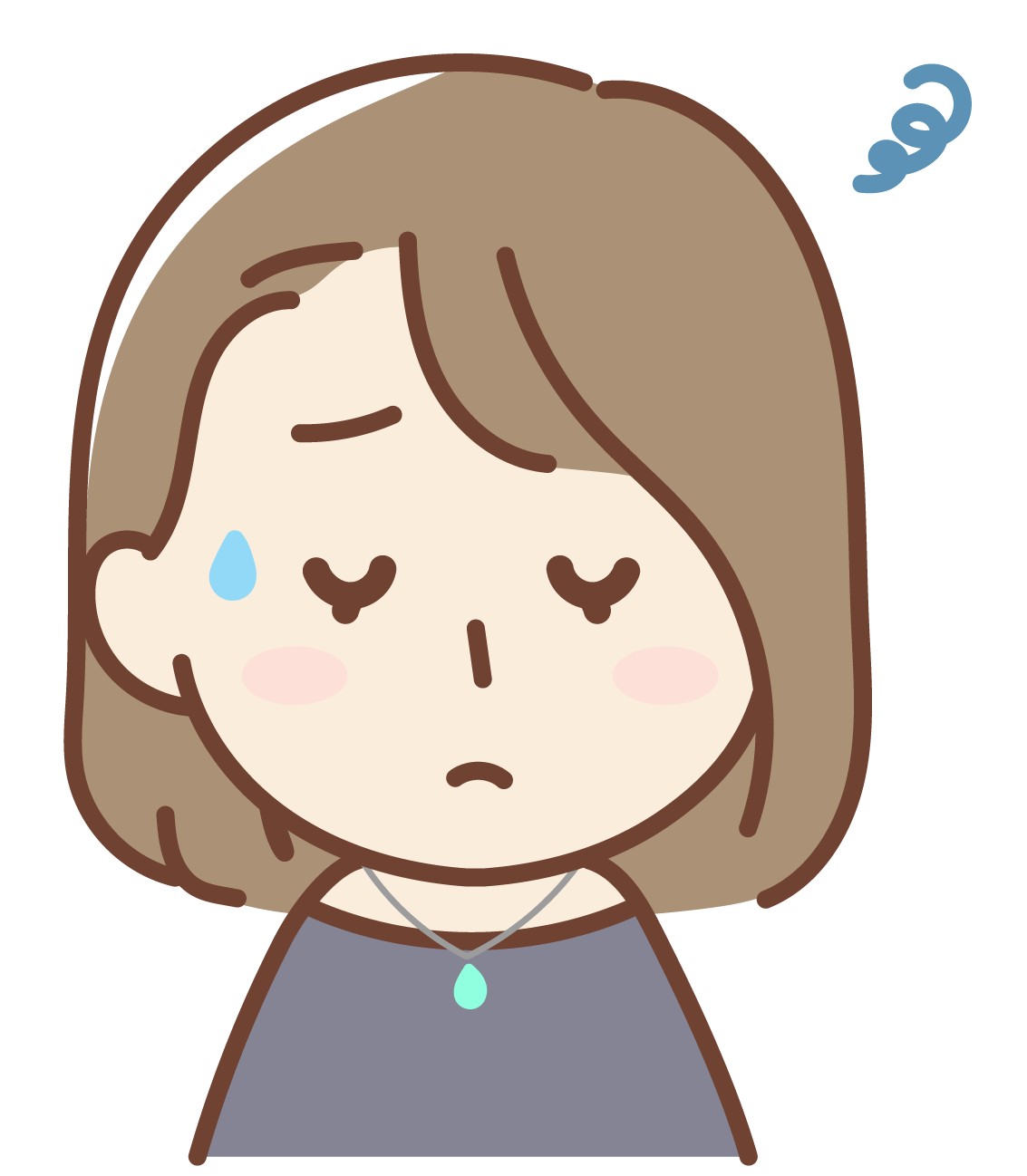
やらせてあげたいけど、時間も心に余裕もない💦
そう感じるのは
多くの親に共通する悩みです。
でも「子どもの自主性を育てたい」と思うなら
まず親自身が
「待つ力」を身につけることが大切です。
「待つ力」とは、
子どもが自分のペースで
成長しようとしているその過程を信じて
急がせず
否定せず
見守る覚悟を持つこと。
もちろん、
すべてを自由にさせる必要はありません。
危険がある時には
「どうしたら安全にできるか」
を一緒に考える。
時間が限られている時には
「今日は時間がないけれど
次の休みにやってみようか」と
子どもの気持ちを否定せずに提案する。

子どもに
「やりたいことが受け止められた」
という実感を与えることが
自主性の土壌を育てるポイントです。
「焦らず見守る」ための心の準備
とはいえ、
焦らず見守るのは
簡単なことではありません。
たとえば、
子どもが洋服を自分で選びたいと言って
季節外れの服を持ってきたとき。
料理を手伝いたいと言って
包丁を持ち出そうとしたとき。

どうしても
口や手を出したくなるのが
親の本音です。
そんなとき、
試してみてほしいのが
自分の中の「心の声」を聞くこと。
「ちゃんとしてほしい」
「失敗してほしくない」
「時間どおりに進めたい」
そんな自分の中の気持ちに
まず気づいてあげましょう。
気づくことで
初めて自分の反応を
コントロールする余裕が
生まれます。
「いま私は、
ちゃんとやらせたいと思ってるな。
じゃあ、それは本当に今、必要なのかな?」
そう問いかけてみると
子どものペースに
合わせる選択肢が見えてきます。
子どもとの「対話」で関係が変わる
見守るといっても、
ただ黙って待つだけではありません。
大切なのは、
子どもと日々の中で
「対話」をすること。
たとえば、こんなふうに
問いかけてみるのもいいでしょう。
「どうしてそれがやりたいと思ったの?」
「やってみてどうだった?」
「どんなところがうまくいったかな?」
「次はどうしてみたい?」
対話は
子どもが自分の内面を言葉にし
自分の行動を振り返るきっかけになります。
また、親に話を聞いてもらえたという経験は
「自分は信じてもらっている」
「大切にされている」
という感覚にもつながります。
ここで大切なのは
「指導」ではなく
「対話」であること。

間違いを正すことよりも
「一緒に考える」
「気持ちを聞く」
ことに重きを置くと
子どもは自分の考えを
深めるようになります。
⚠️親が気をつけたいこと
子どもの「やりたい!」を待つために
親が注意したいこともあります⚠️
「やりたい」を奪う口癖に注意
「どうせできないでしょ」
「まだ早いよ」
といった言葉は、
子どものチャレンジ精神を
萎縮させてしまいます。
代わりに、
「やってみようか」
「どうすればできるかな?」
と声をかけてみましょう。
結果を急がない
「上手にできたか」
「成功したか」
よりも
「自分でやってみた」
経験そのものを大切にしましょう。
失敗しても
挑戦したことを肯定する言葉がけが
自信につながります。
他の子と比べない
「○○ちゃんはもうできるのに」
「お兄ちゃんはカンタンにやれていたよ」
と比べられると
子どもはやる気をなくします。
それぞれのペースを認めてあげることが
安心感を育てます。
まとめ&おわりに
子どもの「やりたい!」は
心の中から湧き出る
大切なエネルギーです。
それを尊重し
信じて
待つことは
親にとって大きな挑戦でもあります。

でも、
「待つ」ことは決して
「放任」ではありません。
親が焦らず見守る覚悟を持ち
日々の対話を大切にすることで
子どもは自分自身の力を信じて
前に進んでいけるようになります。
小さな「やってみたい」を
一緒に喜び
失敗も一緒に受け止めていく。
そんな関係が
子どもの一生の自信と
親子の絆を
育てていくのだと思います。
焦らなくても大丈夫。
今日から少しずつ
「待てる親」になっていきましょう✨




