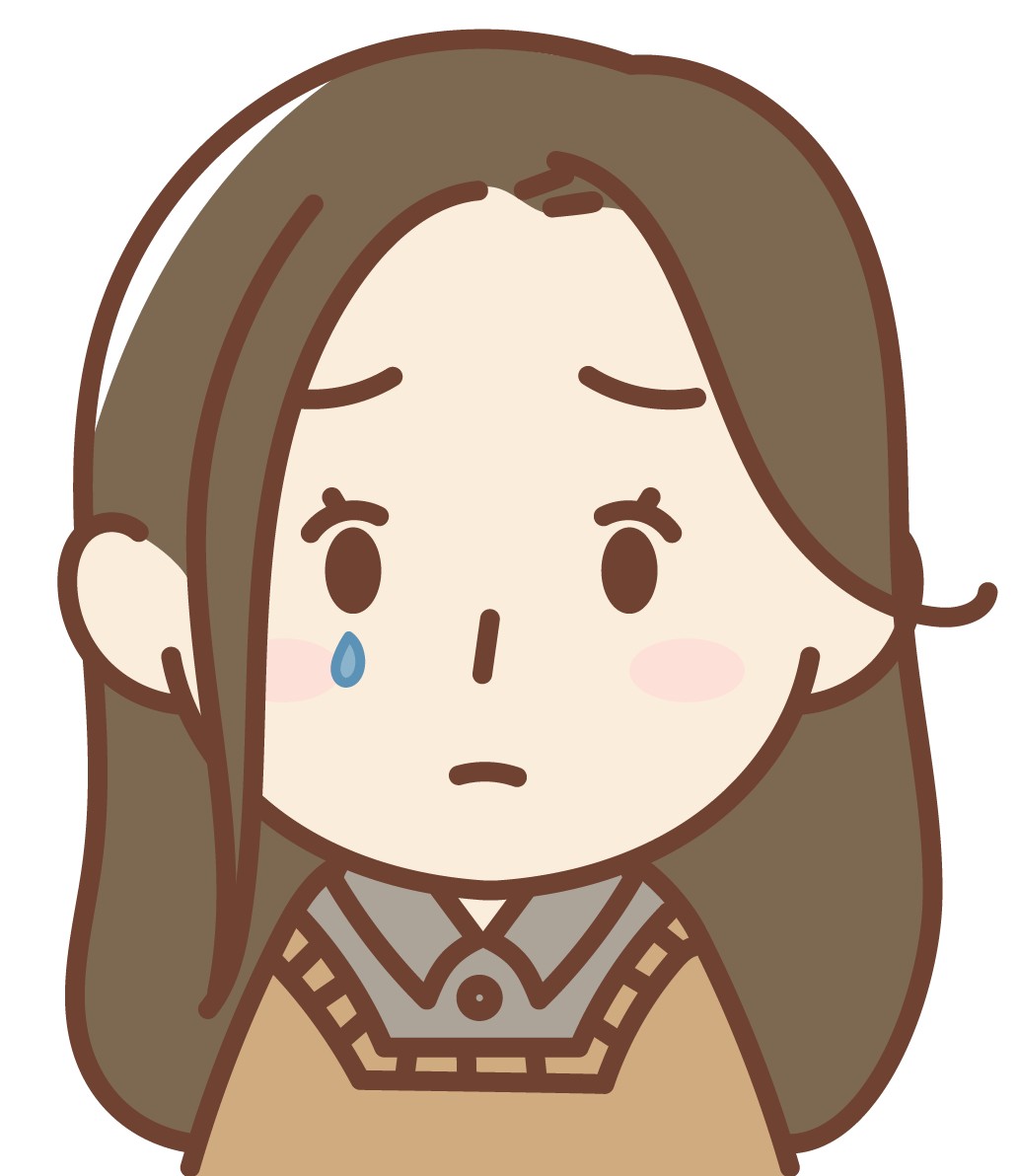
また噛んじゃったんです……💦
カウンセリングの場で
涙ながらに
そう打ち明けてくれたお母さんがいました。
幼稚園年中さんのお子さんが
園で、お友達を噛んでしまった。
先生からは報告と注意があり
さらには他の保護者から
「動物みたいで怖い」
と言われ
心が折れそうになったというお話。
「噛む」
──それは、確かにショックな行動です。
でもそれは、
「うちの子が悪い」からではありません。
そして、もちろん
「あなたの子育てがダメだから」
でもありません。
子どもが噛む背景には
まだ言葉でうまく伝えられない
複雑で繊細な心の動きがあります。

この記事では
「なぜ噛んでしまうのか」
「親としてどう対応すればいいのか」
について、
心理カウンセラーの視点からお伝えします。
なぜ噛んでしまうの?
3〜4歳は
社会との関わりが急に増える時期。
幼稚園で初めて
「他人」との関係を学び始めます。
でも、まだ言葉での表現力が
まだまだ十分とはいえません。
自分の気持ちをうまく伝えられないとき
子どもはどうするか。
言葉が出ないかわりに
「体」で伝えようとするのです。
たとえば、
手が出る
叩く
押す
──そして噛む

噛む子どもは、
実はとても感受性が豊かで
繊細な気持ちを抱えていることも多いのです。
こんな心の声が
隠れているかもしれません。
「取られて悔しかった!」
「遊びたかったのに、入れてもらえなかった!」
「言いたいことがあるのに、うまく言えない!」
「どうしても注目してほしかった!」
それは「攻撃」ではなく
未熟な「表現」なのです。
子どもが「噛む」には、理由があります。
それは単に“いけない行動”なのではなく
まだ未熟な心が
一生懸命に何かを
伝えようとしているサインかもしれません。
「噛む」という行為には
さまざまな意味や背景が隠されています。
その意味をひも解いてみましょう。
感情の爆発──ことばの代わりに体が動く
まだ言葉で
うまく感情を表現できない年齢の子どもは
怒りや悔しさ
悲しみなどが一気にこみ上げると
それをどうしていいか分かりません。

すると、とっさに
「体が先に動く」
その結果が
「噛む」という行動になるのです。
噛んでしまう子どもは
実は気持ちが強くて
まっすぐで
でも繊細な子が多いとも言われています。
自己主張の手段として
「ダメって言いたかった」
「これはぼくのなのに!」
「わたしも仲間に入れてほしかった」

本当は言葉で伝えたいけれど
それがうまくできない。
そんなとき、噛むことで
「私の気持ちに気づいて!」
と訴えていることがあります。
つまり、噛むのは
“攻撃”ではなく
“助けて”という
メッセージかもしれないのです。
ストレスや不安のサイン
集団生活にまだ慣れない
緊張する場面が多い
思うように甘えられない
そんな環境の中で
不安やストレスがたまってくると
「噛む」という形で
それが表れることもあります。
たとえば、
・新しい場所になじめない
・家での変化(引っ越しや赤ちゃんの誕生など)
・親の注目をもっと浴びたい気持ち

こうした背景が
「噛む」行動のきっかけになることもあります。
感覚を使って安心したい
特に3歳前後の年齢では
「口」が世界を感じ取るための
大事な器官です。
なんでも口に入れて確かめるように
噛むことで安心感を得ようとする場合もあります。
これは、いわゆる
“感覚遊び”の一種で
発達段階として自然なもの。
ただし
それが対人関係で出てしまうと
問題行動として見られてしまうのです。
誰かの真似や注目を引きたい行動
兄弟やお友達が噛むのを見て
「それが効果的なんだ」と
学んでしまうケースもあります。
あるいは
「噛んだらみんなが反応してくれた」という
体験が残っていて
無意識に
“注目されたい”気持ちで繰り返すことも。
「うちの子、動物みたい」って言われた…
親としては
この言葉は本当に苦しいですね。
でも、ここで大事にしてほしいのは
「噛んだこと」と
「子ども自身の価値」は
切り離して考えるということ。
噛むという行動は
止める必要がありますが
子ども自身を否定する必要はありません。
むしろ、
「あなたにも理由があったよね」と
子どもの気持ちに寄り添うことで
子どもは
「わかってもらえた」と感じ
安心できます。
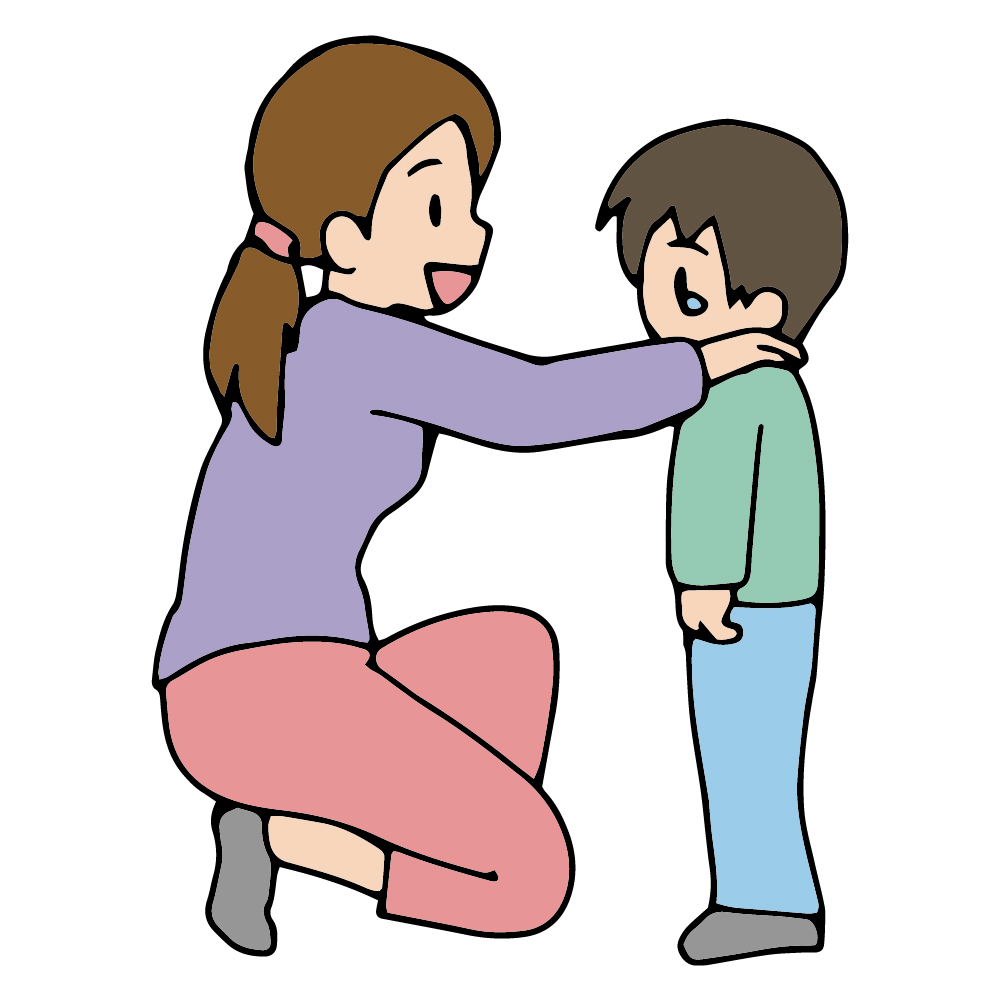
その安心感こそが
次のステップへの力になるのです。
親としてどうしたらいい?
ここからは、親としてできる対応を4つご紹介します。
まずは落ち着いて受け止める
噛んだという事実を聞いたとき
「なんでそんなことしたの!」と
責めたくなる気持ちはわかります。
でも、まずは一呼吸。
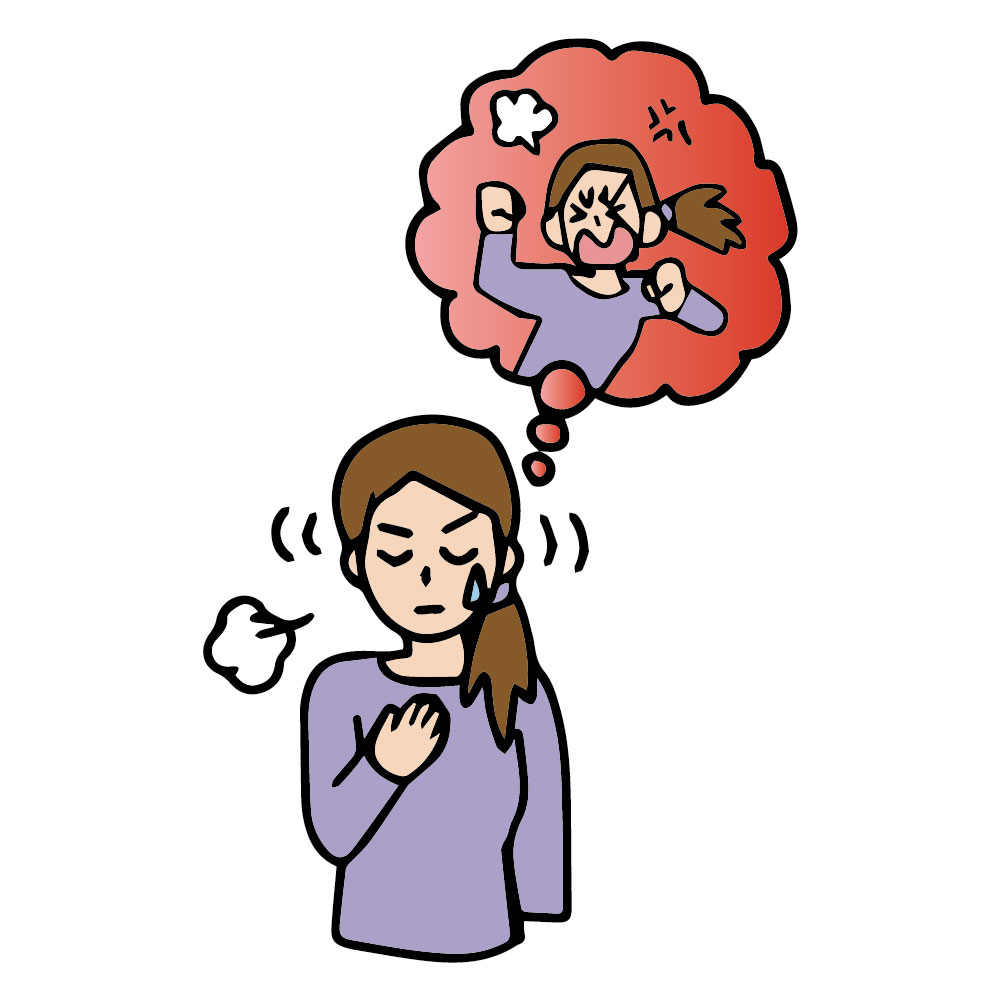
「なにかあったのかな」
「つらかったのかな」と
冷静に受け止めてあげてください。
子どもが噛んだ理由を責めるのではなく
「きっと困っていたんだね」
「どうしたらよかったと思う?」と
一緒に考える
対話の姿勢が大切です。
気持ちを言葉にして代弁する
子どもがうまく言えない気持ちを
大人が代わりに
言葉にしてあげましょう。
「おもちゃ取られて、イヤだったんだね」
「『貸して』って言いたかったのかな?」

こうした代弁を繰り返すことで
子どもは
「気持ちは言葉で伝えられる」ことを
少しずつ学んでいきます。
噛んではいけない理由を伝える
「噛んじゃダメ!」
だけでは伝わりません。
「噛まれたら痛いよね」
「お友達はびっくりしちゃうよね」と
相手の気持ちに
想像が届くように話すことで
「してはいけない理由」が
腑に落ちやすくなります。

ここでは怒鳴ったり
罰を与えるよりも
丁寧な“対話”が効果的です。
「伝える練習」をする
家でも
「こういうときは、こう言おうね」という
ロールプレイをしてみましょう。
たとえば:
「かしてって言ってみようか」
「入れてって言いたいときは、どうする?」
遊び感覚で繰り返すうちに
少しずつ言葉でのやり取りが身につきます。
周りに責められたら…
一番つらいのは
他の親御さんからの
心ない言葉かもしれません。

「しつけがなってない」と
責められたように感じて
申し訳なさや
恥ずかしさに
押しつぶされそうになることもあるでしょう。
でも忘れないでください。
あなたは、
子どもの行動を正そうと
真剣に向き合っています。
その姿勢こそが
何よりも価値のある“子育て”です。
誰しも、
子どもを通して学んでいくのです。
完璧な親も、
完璧な子もいません。
間違ってしまったあと
どう向き合うか──
そこに大切な育ちがあるのです。
まとめ&おわりに
・噛む行動の背景には
「伝えられない気持ち」がある
・「行動」は止めるが
「子ども」を否定しない
・落ち着いて、気持ちを代弁してあげる
・噛んではいけない理由を
「対話」で伝える
・言葉で伝える練習を
日常に取り入れてみる
・周囲の言葉に傷ついたときは
信頼できる人に気持ちを話してみる
子どもの困った行動は
「成長のチャンス✨」でもあります。
噛んでしまったその経験を
どう育ちに変えていくか。
親子で一緒に歩んでいけるように
そっと寄り添う力を
育てていきましょう🌿




