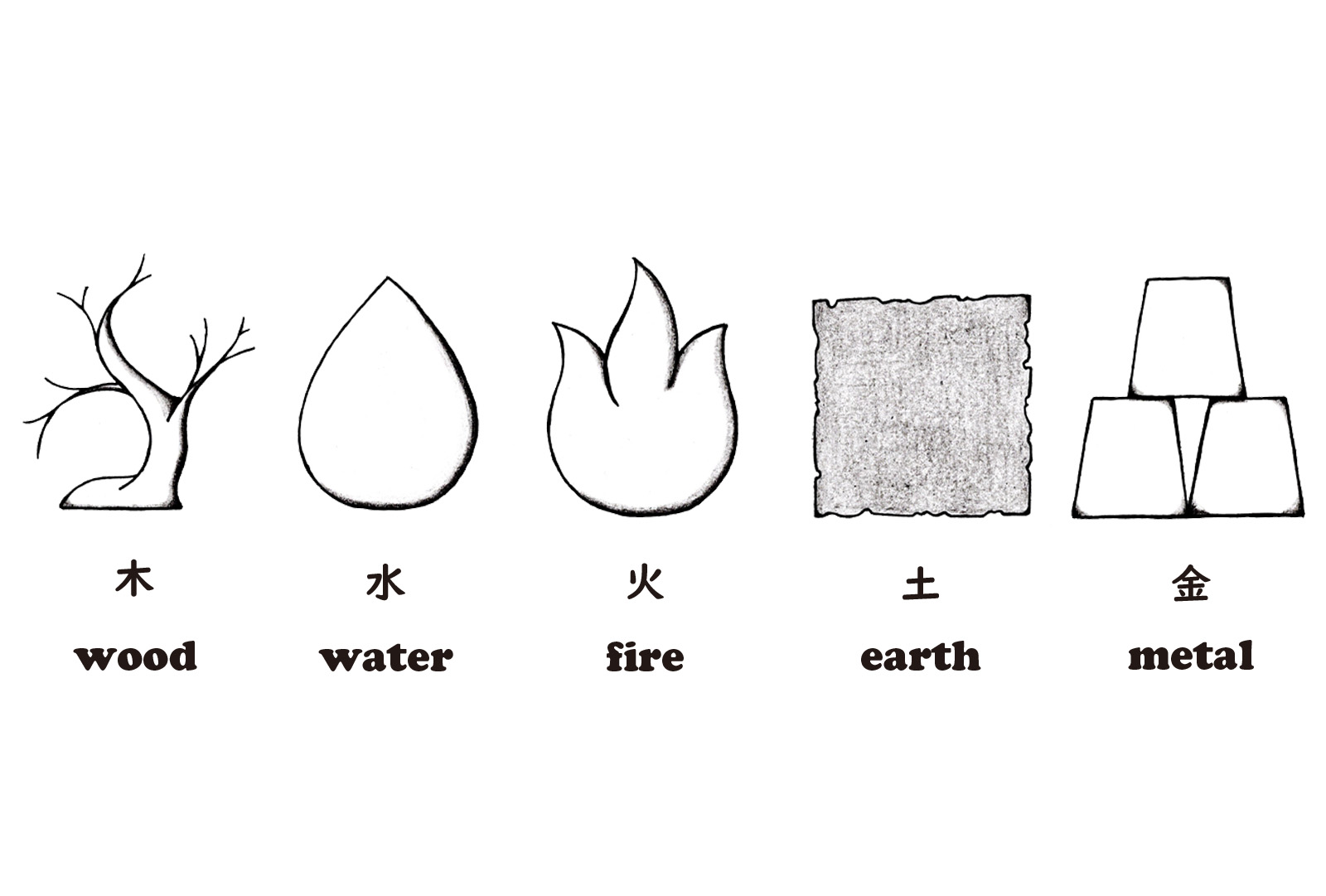これまで漢方の”ものさし”あれこれを
まとめていきました。
漢方は
中国医学(中医学)が発祥であり
日本で独自に発展してきたものです。
発祥が中国ということもあって
やはり中国思想や哲学が
色濃く反映していますね。
そんなところも
面白いところ♬
いかに生活に根深く
関わってきたのかが伺い知れて
興味深く感じられます。
「気血水理論」
「陰陽」を主軸とした「八鋼弁証」
それらに続き
有名な中国思想である「五行説」について
勉強していきたいと思います!
この「五行説」が理解できると
「五臓五腑」または「五臓六腑」という
私たちにも聞き覚えのある言葉や
考え方にも関連していくので
楽しんで勉強していきましょう!!
中国思想「五行説」とは? ?
「五行説」とは
自然界のあらゆるもの全ての現象は
五つの要素に分類でき
その五つの要素は
相互に深く関係しあっている
という考え方です。
「気血水」が
3つの要素をチェックする”ものさし”だったのに対して
「五行説」は
カラダを支える5つの要素でチェックする”ものさし”です。
五つの要素「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)」
五つの要素とは
木(もく)
火(か)
土(ど)
金(こん)
水(すい)です。
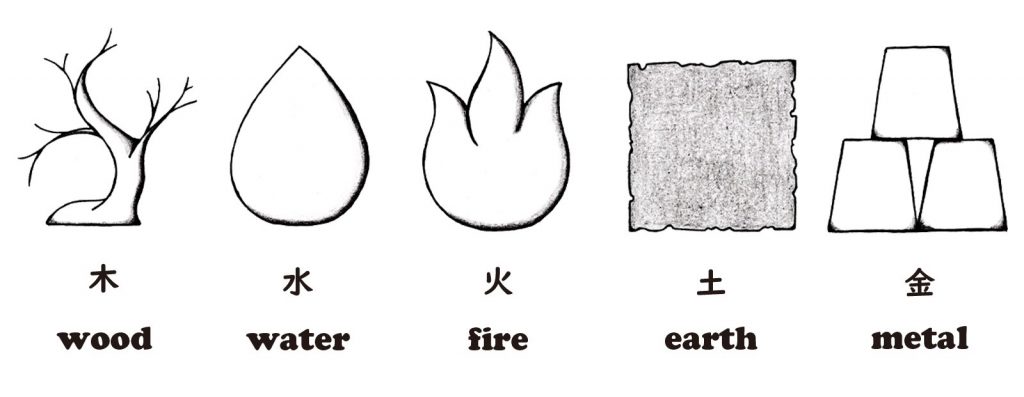
それぞれを自然界の現象にあてはめてみると
・木…樹木が成長し幹や枝が伸びていく状態
→伸展・上昇を表す
・火…炎が熱く燃えている状態
→温熱・上昇を表す
・土…土から植物の芽が出るように育て育む状態
→万物を生かす
・金…熱によって固いものを任意の形にすることができる
→変革を表し、清潔、収斂の意味を持つ
・水…低いところに向かって流れる様子
→冷たい、潤すという意味を表す
「五行説」の特徴、相合・相克関係
この五つの要素の関係は大きく分けて
「相生(そうせい)関係」
「相克(そうこく)関係」
という二つの関係があります。
相生関係(そうせい)
「相生関係」とは
お互いの性質や働きを生かし助け合う関係です。
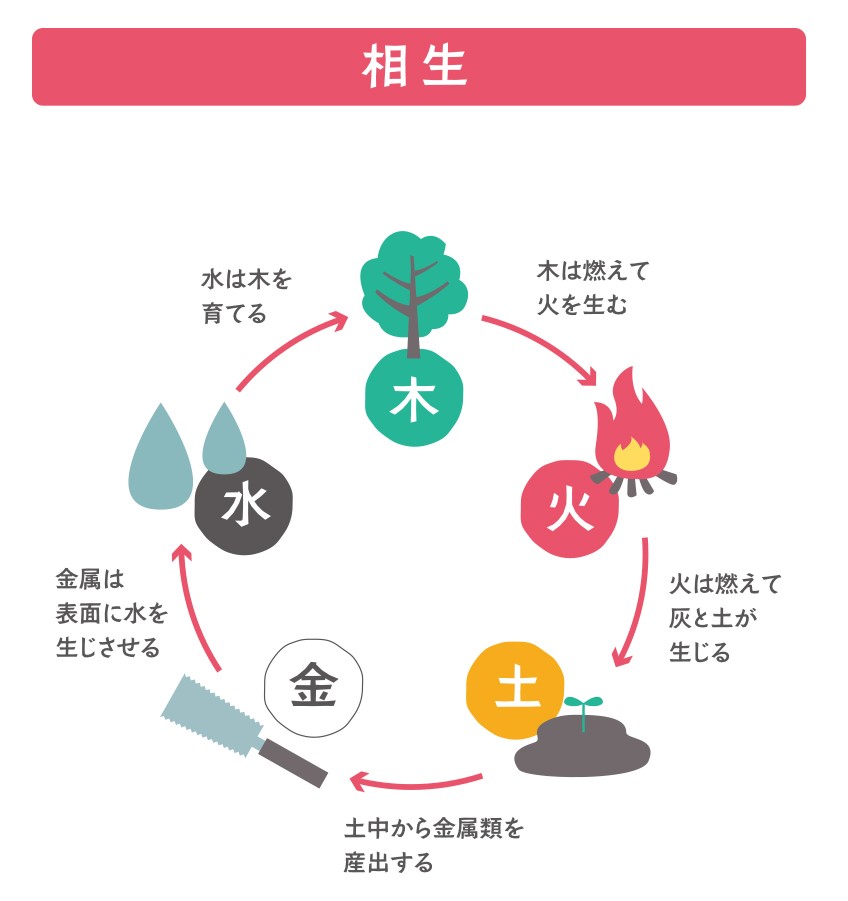
・木を擦り合わせると火が生じます(木生火)
・火が燃え尽きると灰になり、やがて土となります(火生土)
・土の中から金(金属)が生じ、掘り出されます(土生金)
・金(金属)の鉱脈に沿って、水が生じます。
または金には水滴が生じ、やがて水が生まれます(金生水)
・木が育つには水が必要です(木生水)
このように「相生関係」では
五つの要素が
お互いを助けるように巡っています。
相克関係(そうこく)
「相生」とは反対に
「相克関係」とはお互いを抑制しあう関係です。
相克関係では
五つの要素を五角計上(☆型)に
並べたとき向かい合っている二つの関係の中で
見ることができます。
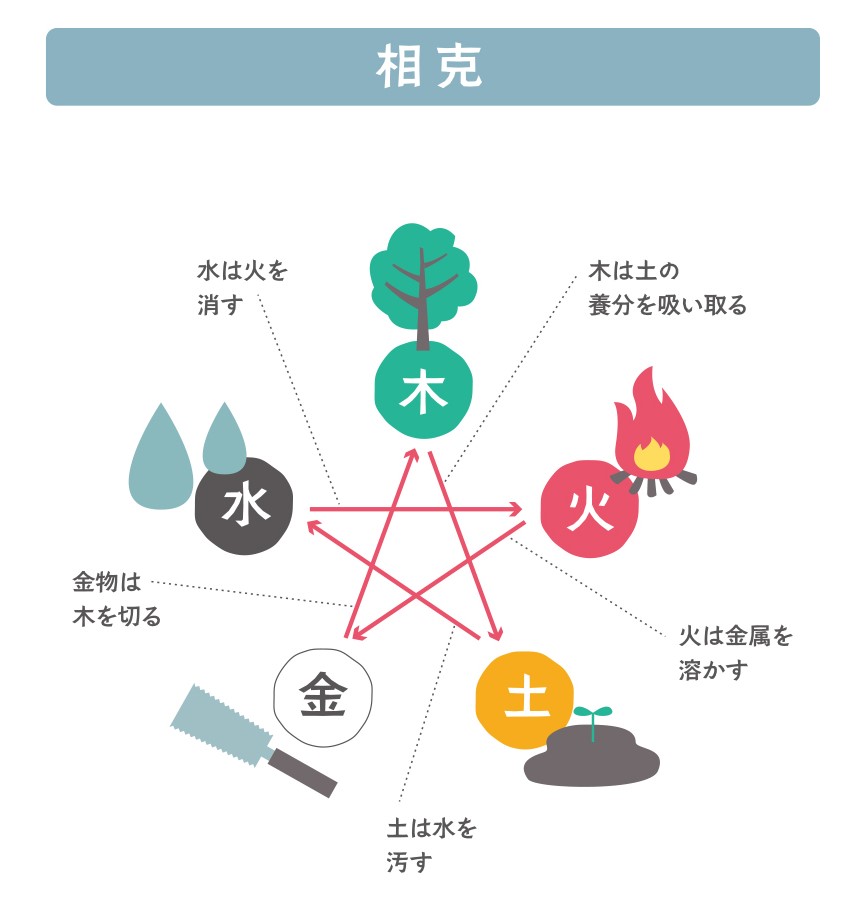
・成長し続ける木は土から養分を吸い取ります(木克土)
・土がたくさん積み重なると水の流れをせき止めます(土克水)
・水は火を消します(水克火)
・熱い火は金属を溶かします(火克金)
・金属を加工した刃物は木を切ります(金克木)
単体では存在せず
お互いが協力し合い
もしくは抑制しあいながら存在するのが
面白い所ですね♬
その関係性も
子供にもわかりやすいような
単純でかつ明快さがありますね。
昔から伝わり
それが廃ることなく
今も続いていっていることが
漢方のスゴい所!!
まだまだ入り口ですが
楽しみになってきました。
一緒に勉強していきましょう!!\\\٩( ‘ω’ )و ///